PR
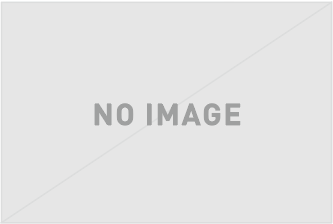
| 住所 | |
|---|---|
| アクセス | |
| 営業時間 | |
| 最寄駅 | |
| 電話番号 |

北海道は、日本の中でも離れ島であるため、北海道ならではの郷土料理やおすすめ名物グルメがたくさん存在しています!また、先住民族である、アイヌ民族の料理もありますので、それらにつて詳しく紹介します。また、メジャーな郷土料理ではない、少し珍しい郷土料理も紹介しますので、最後まで読んでみてください。

北海道の郷土料理と言えば、一番に思い浮かぶのが「ジンギスカン」ではないでしょうか。北海道民には広く愛されており、特別な日はもちろん、日常的にジンギスカンを楽しみ人気なのです。ジンギスカンは、羊のお肉を使われているのですが、中にはクセが強くて食べられないという方もいるようです。
ジンギスカンの発祥は、東京都言われていますが、明治時代に食用を含まれる綿羊を北海道の各地で飼育が始まったことで、北海道の郷土料理として広く知られるようになりました。名前は、モンゴル帝国の「チンギス・カン」が由来とされていますが、諸説あるので本当のところ闇の中です。
ジンギスカンには、タレ付きジンギスカンと焼いた後にタレにつけて食べるジンギスカンの2種類があり、地域によって食べ方は変わります。例えば札幌では焼いた後にてれにつけますが、旭川ではタレ付きジンギスカンを焼いて食べます。もやしや玉ねぎなどの野菜と一緒に食べるのが主流です。鍋は中央が膨らんだ特別なものを使いますが、北海道では一家に一台その鍋があることでも有名です。

石狩鍋は、鮭を主材料とした味噌味の寄せ鍋のようなものです!味噌味なため、塩漬けされていない鮭を使用するのが一般的です。名前の由来は、秋に鮭が遡上する石狩川だと言われています。元祖石狩鍋と言われているのが、石狩市・石狩川付近にある割烹「金大亭」です。明治時代の石狩鍋とも言われていて、口コミでもとても有名なお店です。
石狩鍋の始まりは、味噌汁の中にお店で使えないシャケのアラやぶつ切り、たくさんの野菜を入れて煮込み、賄いとして出されていたことだそうです。賄いや漁師飯だった石狩鍋に、玉ねぎやキャベツなどの西洋野菜や鮭の臭みを消すために山椒を使用するなど、金大亭がアイディアを出し世に送り出されたのです。
また、9月15日は毎年「石狩鍋記念日」に制定されており、石狩市内の飲食店が集まって結成された「あき味の会」が、日本記念日協会に申請し、2008年に正式に記念日として認定されました。

鮭のちゃんちゃん焼きは、北海道の漁師町発祥の甘しょっぱい味噌味の名物です。鮭がメインの料理ですが、ホッケやニジマスなど他の魚がメインになる場合もあります。最近では、ラム肉のちゃんちゃん焼きも人気のようです。
「ちゃんちゃん焼き」という名前の由来は、「ちゃっちゃ(素早く)と作れるから」や「父ちゃんが作るから」や「料理する際にちゃんちゃんと音がなるから」などなど諸説あります。鮭の他には、ピーマンや白菜・人参など使われる野菜は家庭によって違いはあります。また、ホットプレートなどの鉄板で料理されるのが主流で、少し豪華な晩御飯のメニューというイメージがあります。
調理方法は、たくさんの野菜の上に鮭の切り身や三枚おろしを乗せ、味噌・酒・みりん・砂糖の合わせ調味料をかけ蓋をして煮込むのがおすすめの方法です。しかし、正式な料理方法は、油を引いた鉄板の上に鮭を見から焼き、火が通ったらひっくり返し、合わせ調味料を塗り野菜をのせて弱火で火を通すと、おいしいちゃんちゃん焼きが出来上がります。

いかめしは、ゲソを落とし腹わたを取り出した胴の部分に、研いだ米を詰め醤油ベースのだし汁で炊き上げたものです。発祥は、函館本線森駅の駅弁業者が、第二次世界大戦中に米が不足していた頃、米を節約して満足感のある食べ物をと考案しました。また、米の代わりにジャガイモを以下の中に詰めて炊いたものも、松前町や焼尻島などの日本海側で食べられていました。
戦後に京王百貨店で行われた「第1回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」に出品され、第2回には売り上げ第1位になり、森町の名物として全国へと広まっていったのです。
現在では、函館名物(森町名物)としてとても人気があり、函館旅行に行くと必ずお土産として買って帰るほどの人気ですので、お土産にとてもおすすめです。

北海道といえば、新鮮でおいしい海鮮物が人気です。その中でも北海道のいくら丼も北海道の名物として人気があります。特に有名なのが、世界自然遺産としても知られる知床半島で食べるいくら丼です。ぷりっぷりのいくらをふんだんに使った新鮮ないくら丼は絶品なのでとてもおすすめです。
また、ウニ丼やうにいくら丼などの贅沢な海鮮丼も名物として存在しています。地元の人間にも人気がある、本場北海道のいくら丼をぜひ1度堪能してみてください。

北海道では、牛肉よりも豚肉がよく食べられています。その中でも豚丼は砂糖と醤油で作られた甘ダレを使用しており、帯広などのとかちが発祥の地を言われています。
帯広の方に行くと、豚丼の有名で人気なお店がたくさんあり、中には1時間以上並ばなければ食べられないほどの名物店も存在しています。豚丼に使われる豚は、フライパンで焼くのではなく、炭火で焼きあげていることもポイントです。最後は、お好みで山椒をかけて食べると、甘ダレと山椒のピリッと感がマッチして、まさに絶品です。

「赤飯なんて、全国各地どこにでもあるもの」と思われるでしょうが、北海道の赤飯は、一味違います。一般的な赤飯は「あずき」を使用しますが、北海道の赤飯は「甘納豆」を使用し食紅でピンクに色付けられているのです。開発者は、札幌市にある「光塩(こうえん)学園女子短期大学」元学園長の故・南部明子先生のお母様です。
光塩学園は、現在は食物栄養科と保育科が設置されているのですが、食物栄養科の授業の中で甘納豆を使用した赤飯の実習が組み込まれています。故・南部明子先生のお母様は、子供達でも食べられるように甘くておいしい甘納豆を使用し、食卓に並べられたが始まりです。
その後、北海道のTV番組やラジオ番組等で紹介されたことがきっかけで、北海道の赤飯は、甘納豆が主流になったのです。甘納豆を使用しているのでとても甘いのですが、そこへ仕上げにごま塩を振ることで、ちょうど良いバランスの赤飯になります。

松前漬けは、数の子・スルメ・昆布などを醤油に漬け込んだ保存食として知られる北海道の名物です。発祥は名前の通り松前藩・現在の松前町です。現在では醤油ベースのものが主流ですが、江戸時代後期には、塩に漬け込んだものが主流でした。
松前漬けは、ご飯のお供としても人気ですが、年配のお父さんやお酒付きに方には酒のつまみとしてもとても人気があります。また、保存が効くものなのでお土産としてもおすすめです。数の子・スルメ・昆布が入っているのですが、手作りする場合には、人参や生姜も千切りにしてつける家庭もあるようです。

三平汁は石狩鍋とよく間違われるのですが、石狩鍋とは違い、昆布で出汁を取った塩ベースの汁です。具材はタラや鮭、ホッケ、ニシンなどをメインにし、ダイコンやゴボウ・人参・ジャガイモなどの根野菜と一緒に煮込みます。
地域によって少々違いがあり、道北ではタラがメイン、日本海側では糠ニシンがメイン、道南では酒がメインで味噌ベースのものを味噌三平と呼び、スケソウダラがメインの塩ベースのものを塩三平と読んでいます。
発祥や由来は定かではありませんが、古くから北海道の名物であることは間違いなさそうです。一番古い文献は、1784年の平秩東作の東遊記に、「サンヘイ」という名前で載っています。

いももちは道産子の子供達を支えるおやつの代表格です。いももちと似ているもので、いもだんごというものもありますが、明確な違いはわかっていません。また、和歌山県や高知県・岐阜県にもいももちと呼ばれる郷土料理はありますが、作り方や材料に違いがあります。
北海道のいももちは、茹でたジャガイモの皮を剥き綺麗に潰します。その後片栗粉を適量混ぜて丸めて焼き上げます。醤油ベースの雨だれにつけて食べるのが主流です。ジャガイモなので腹持ちがよく、小腹が空いた時に最適です!
発祥は、もち米が不作だった時代にジャガイモやかぼちゃに片栗粉を混ぜて作ったものを餅の代わりとして食べられていたそうです。現在では、サービスエリアや居酒屋などでおすすめのメニューなのです。

画像は伝統的なアイヌ料理であるユック丼(エゾシカ鹿肉丼)と呼ばれる料理です。
アイヌ民族は北海道の先住民族として知られており、伝統的なアイヌ料理も北海道の郷土料理です。アイヌ料理は、鹿やヒグマ・鮭などの動物やドングリや山菜などの山で採れるもの、畑で育てたジャガイモなどの農作物が使われます。
主なアイヌ料理は「オハウ」と呼ばれる煮込み料理です。野生動物の肉や魚・山菜・野菜を煮込んだ鍋料理なのですが、三平汁や石狩鍋の期限とも言われているのです。
出汁は、野生動物の骨や小魚を焼いたものを使い、その後具材をたっぷりと入れ十分な時間に混みます。煮込んだ際に出る「アク」は薬の成分があると言われているので取り除かないのがアイヌ流です。最後に少量の塩や焼き昆布の粉末を入れて出来上がりです。

星の降る街とも呼ばれている芦別市の名物です。小麦粉を練った団子やたけのこ・しいたけ・豚肉・こんにゃくなどを用いたとろみのある中華風のスープなのですが、現在では、ガタタンラーメンと呼ばれるものがとても人気です!
由来は満州国の「疙瘩湯」が原型と言われていて、戦後ある人物が持ち帰り、日本風にアレンジして芦別市でデビューさせたのが始まりだそうです。現在では商標登録もされており、北海道の名物に仲間入りしたのです。

現在では全国各地で食べられているスープカレーですが、発祥は北海道・札幌とされています。1971年に札幌の喫茶店「アジャンタ」で発売された「薬膳カリィ」が始まりと言われています。薬膳カリィには具材は入っておらず、多くの人が勉強のためアジャンタを訪れるようになったどうです。
その後1993年に「スープカレー」という名前が決められ全道・全国へと広がっていきました。現在では、札幌市には200を超えるスープカレーのお店があり、地元民はもちろん観光客にも人気の料理なのです!
また、苫小牧市には「ホッキカレー」という名物もあります。苫小牧市はホッキの水揚げ量は日本一なので、ホッキを使ったカレーを発売し始めたようです!地元民に人気のホッキカレーを、一度試してみてはいかがでしょう。

北海道には、おすすめのおいしい郷土料理がたくさんあります。古くから伝わるものから最近生まれたものまで様々ですが、どの料理も自信を持っておいしいと言えるものばかりです。北海道にお越しの際には、北海道郷土料理を召し上がってみてください。